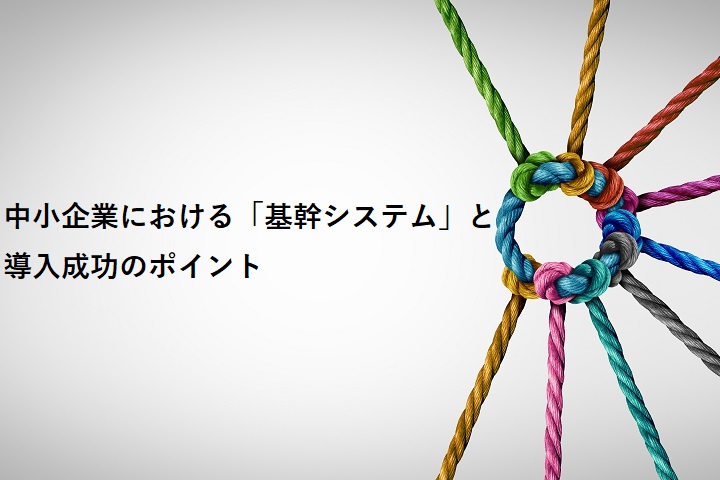「基幹システム」導入を検討されている会社さん、多いと思います。おそらくこれから
- どのシステムがいいんだろう
- どのベンダーに頼んだらいいんだろう
- どうやって進めたらいいんだろう
こんなことを考えていくことになるはずです。
そこで今回は私の経験から、まずは「基幹システム」とは何を指しているのか視点を一致させるためのアドバイスと、導入成功させるためのポイントについて書いていきたいと思います。
基幹システムとは
基幹の意味するところ
この場合の「基幹」という言葉は、英語のコア(core)を指しています。
企業活動に合わせて表現すると、こんな意味になります。
システムがストップする(使えない)と、業務が思うように回らなくなる
基幹システムの領域
主に次のような業務領域をこなすシステムがすでに世の中に存在します。
- 販売管理:受注、見積り、納品、請求、売上・売上管理、入金管理
- 在庫管理:入出庫、棚卸、在庫管理
- 購買管理:発注、仕入、仕入先管理
- 生産管理:生産計画、製造指示、工程管理
- 会計管理:仕訳、台帳、決算、財務レポート出力
- 給与管理:勤怠、給与計算
- 人事管理:人事情報管理
- 営業支援:見込み客、セールス活動、案件進捗などの管理
業種別に深く見ていくと、もっと細分化されたシステムもあります(建設関係だと「出面管理システム」とか)。
中小企業における基幹システムとは
基幹システムというと、「会社で発生する業務全部の面倒をみるシステム」。こんなイメージをされることがあります。確かに業務活動の中心を担うシステムなので間違いではありませんが、中小企業様ですともう少し面倒をみる領域を狭めた方が良いです。
例えば、大企業ですと「ERP」と呼ばれる、各業務の処理機能をワンパッケージにしたシステムを導入することがあります。私も過去にERP導入を行ったことがあります。
その時に感じたのは「ERPは使う側も難しい」ということと、大企業特有の「言い訳無用」なトップダウンパワーが発揮できないと難しいということ。
こういった経験から、私が中小企業様にお勧めする基幹システムの条件とは、
- 業務単位のパッケージソフト(導入しやすく使いやすい)
- パッケージソフト同士でデータのやりとりができる(これはホント素晴らしい)
- ERPのような経営戦略機能まで用意されたフル機能は後回しでOK
- 自社向けのカスタマイズが必要な部分は、Excelやkintone、Accessなどを使って別開発で対応
こういうのが良いと思っています。というのもフル機能を持ったERPをいきなり導入しても、備わっている機能を全部使えるかどうか不明だから。
それなら、スモールスタートで段階的に業務をシステム化する方が失敗も減りますし、導入されたソフトウェアを使うスタッフさんの負担も減ります。そして、最終的に段階を踏んで導入した業務システム同士を連携させ「基幹システム」として構成させる方法が合っていると思います。
どこから手をつけるべきか
経験から申し上げるなら、以下の3つから始めるのが成功へのポイントだと考えています。
- 会計管理
- 給与管理
- 人事管理
なぜなら、これらの業務にはシステム導入しやすい傾向があるからです。
- 傾向1:会社内での手続きルールはあれど、会計も給与も人事も「国」が決めたルールに沿って処理される部分がほとんど
- 傾向2:これらの業務を担っているスタッフさんは流れや手順やルールが決まっていると「変化すること」への順応性が高い
- 傾向3:仕事の流れをシステムで変化させても他の部署からあまり注目されない
さいごに
説明会などで話だけ聞くと、大掛かりな基幹システムは「スゲー便利!経営に有利!」という感想を持つはずです。しかし、実際に導入するとなると、
- 課題山積み
- 落ち着いて考える時間なし
- 社内の雰囲気最悪
こんなことが発生しがちです。いくら良いと言われるシステムでも、自社で使えなくては意味がありません。基幹システムの導入は良いことですが、自社で使って効果が期待できるシンプルな基幹システム導入を意識しておきましょう。
間違っても検討段階から「システムを自社向けにカスタマイズすることが前提」という考えを持ってはいけません。検討段階では、提供されているシステムに「自社の業務をどこまで一致させられるのか」という視点で考えないと導入費用やメンテナンス費用が膨らむ「困ったシステム」を導入することになります。