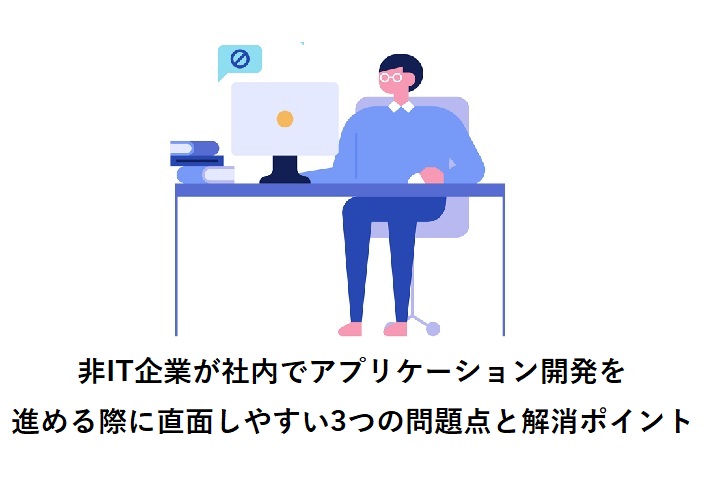IT企業ですとアプリケーション開発を進める際に「当たり前」になっていることが、非IT企業ですと「後回し」「何とかなる」「無くてもいい」という考えが「社内での正解」になってしまうことがあります。
でも、間違った「社内での正解」を続けていると、アプリケーション開発が進まないこともあれば、後から修正や保守ができない状況を作り出してしまう可能性が非常に高いです。
今回は、非IT企業様が社内アプリケーション開発を進める際に直面しやすい問題点と解消のポイントをお話します。
非ITの中小企業様で直面しやすい問題点3つ
- 開発スキルやノウハウの不足
- 要件定義の曖昧さやコミュニケーションのギャップ
- 保守や運用の体制が曖昧
ひとつずつ問題点の課題と解消ポイントとなる対策を見ていきます。
開発スキルやノウハウの不足
課題
IT業が本業ではありませんので、どうしても
- 開発経験
- 設計ノウハウ
- テストノウハウ
これらが不足気味です。また、以前にやったことがあったとしても、社内に情報や知識が蓄積されていないケースが多いため、過去の経験やノウハウを役立てることが難しいです。
結果
こうした課題によって、次のような結果を招くことがあります。
- 設計ミス(現場で使えない)
- 品質の低いコード(後からメンテしづらい)
よくあるのが、こういう状態です。
「アプリ開発は終わったけれど、現場で使えないものが完成した」
「アプリ開発は終わったけれど、仕様変更や障害対応で手間取る」
こうしたアプリケーション、結局は現場で使われないままになります。
対策
3つの対策があります。
- 内製支援を行ってくれるベンダーを活用
- フリーランスを活用
- 「型」を決めて「小さくスタート」する開発手法を選ぶ
要件定義の曖昧さやコミュニケーションのギャップ
課題
非IT企業様のスタッフさんが担当してアプリ開発を進めると、
- 開発担当と業務担当との間で認識が合わない
- 現場の業務知識をシステム開発向けに設計できない
アプリ開発でもっとも重要なのは、プログラムコードを書くことではなく「要件定義」です。そして、良い要件定義を行うためには、担当者間のコミュニケーションが必要になってきます。
結果
この課題によって、次の結果を招くところ、、、多いです。
- 現場が期待しているものと全く違ったものが完成する
- 作ったのは良いけれど、後から大量の修正が発生して辟易する
- 「使いやすさ」の解釈がズレたままになる
対策
- 手書きで良いので業務フローを描き認識を揃える
- 業務知識と技術知識の橋渡し(パイプライン)役を設ける
- 要件では「なぜそれが必要なのか」を明確にする
保守や運用の体制が曖昧
課題
アプリ開発は完成したら終わりではありません。動いている限り、保守と運用が必要です。しかし、多くの非IT企業様では開発はガンバルけれど、
- 開発後の継続的な改善
- 運用時のトラブル対応
安定して使い続けるための仕組みが不十分です。
結果
この課題によって発生する結果は次のとおりです。
- 障害対応が滞る
- 機能追加ができない
- 担当者の異動や退職で「誰にもわからない」状態に
こうなると使っている現場からの信頼は低下。結局は元の「手作業」に戻ることになります。
対策
- アプリ開発のときから「保守と運用」の目線を忘れない
- アプリケーションの動きが「見える化」されるようにする
- ドキュメントや手順書の整備と共有
さいごに
「アプリケーションを作るだけ」なら、そんなに難しくはありません。難しいのは「作った後も安定して使い続けられる」仕組みを開発時から取り入れていくことです。
30年以上の経験から申し上げるなら、社内で開発するときには専門家に参加してもらい、連携しながら進めていくのが本当の意味での成功につながると思います。
というのも、社内で詳しい人が在籍しているとしても、私のように30年以上の期間の中で300社以上のアプリ開発や保守・運用を経験された方が在籍されている事例は少ないと思います。
こうした現場経験から実際に使える引き出しの多さからも、専門の人の参加を検討されるのが得策だと思います。