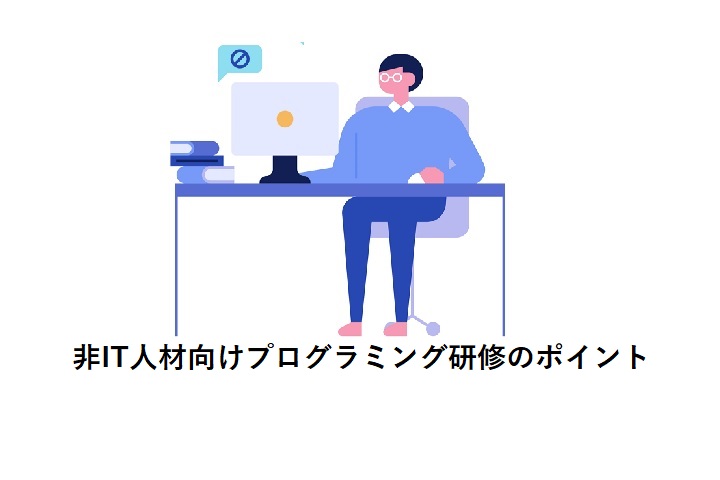IT人材を募集しても集まらない。応募がない。面接まで進めても最後は断られる。
こうした経験をされているIT業ではない会社さん、多いと思います。
そこで次に意識されるのが、IT人材を獲得するのではなく、「IT人材に育てよう!」という試み。
非IT人材をIT人材に育てるためには研修内容や流れにポイントがあります。
どうして日比野が偉そうに言えるのか
事業者情報ページをご覧いただくとわかりますが、私は非IT人材向けにプログラミングに関する書籍を3冊執筆しています。そして、これら3冊の中の1冊は海外で翻訳され出版されました。
さらに、最近は個別には行っていませんが、プログラミング学習事業で講師をしていた時期があります。
こうした実経験から、非IT人材がプログラミングを学習する場合には、研修内容や流れによってスキル獲得に近づけるポイントがあることを知りました。
学びやすいものを選ぶ
プログラミング言語や学習環境(ツール)は重要です。最初から難しい言語や複雑な環境を使うと、面倒になって挫折します。
今の時代に即した「おすすめ」はというと、
- VBA(ExcelとかAccessを動かす言語)
- Python
- Kintoneなどのノーコードツール(または、ローコードツール)
ここでのポイントは、IT企業へ入社するのではなく、IT企業のようにシステム開発を外部から受注しませんので、自社業務で使いやすい言語や環境を選ぶことです。
教材と演習は「業務」前提
学習するためには教材や演習が必要になってきます。
プログラミング学習の教材や演習となる書籍や動画には、多岐にわたるジャンルが存在します。
- ゲームを作ろう
- オンラインショップを作ろう
- 業務で使えるツールを作ろう
こういうのがあります。当然ですが「業務」に近いことが学習できる教材や演習を選ぶことです。
いくらゲームの作り方を学習しても、顧客管理業務向けのアプリケーションは作れません。
学習期間は短く
だらだらと学習してもスキルにつながりません。なぜなら「すぐに忘れるから」です。プログラミング学習は「短期集中」がおすすめです。
例えば、1~2週間は徹底的に基礎部分の研修を行い、その後は実務で使えるように進めるのが効果的です。
令和には流行らないかもしれませんが、プログラミングは「学びながら作る」ものと考えましょう。いくら頭の中で考えていても、実際に作っていかないとスキルになりません。
フォローできる環境を整える
プログラミング学習者は100%つまづきます。必ずエラーと遭遇し頭を抱えます。
そういったとき、社内でフォローできる環境を用意しておきましょう。例えば、
- 社内で少し詳しい人がいるのでフォロー担当になってもらう(通常業務外なので手当を出しましょう)
- 社外で詳しい人がいるのでフォロー担当として協力してもらう(依頼するのなら費用を払いましょう)
- 外部の専門家にフォロー担当として参加してもらう(費用が発生します)
この体制が無ければ、学習者だけで全ての問題を解決することは難しくなりますし、解決までに多くの時間を使ってしまうことになります。すると、人はだんだんと嫌になって「もういいや」となります。
PythonやVBAでの研修例
あくまでも「業務」で使うことだけに絞って考えます。
ステップ1
プログラミングの基礎の基礎を学びます。具体的には、
- データ型
- 変数
- 条件分岐
- 繰り返し
- 四則演算
ステップ2
ファイルの読み込みと書き出しを学びます。
業務では「CSV形式」「Excel形式」のファイルを読み込む・書き込むことが多いからです。
ステップ3
データからグラフを作る。これも業務で多い要望です。
ステップ4
データから、何らかの条件に合わせて集計するプログラムを作ります。
自動集計の要望も業務では多いです。データを集計するプログラムを作ると、
- 集計機能の作り方の手順(ほとんどは同じ)
- いらないデータの排除の仕方
- 重複しているデータの扱い方
- 複数のデータを扱う場合は、データ整形の方法
こうした「業務で使うことが多い」機能の作り方を学べます。
ステップ5
作ったプログラムを実際の業務に沿って「テスト環境」で使ってみます。正しく動かない場合は、プログラムを修正します。
ステップ6
動いてからが本番です。改善する点を考えましょう。
改善点があれば、動いているプログラムを改修していきます。
ステップ7
改善したプログラムをテストし、正常に動けば業務で使っていきます。
さいごに
非IT人材育成でもっとも難しいのが「学習者へのフォロー」です。
なぜなら、学習者が作ったものを理解した上で、正しい方向へと導かないといけないからです。これは「他人が書いたプログラムを理解する」スキルが必要になります。
ぜひ「フォロー体制」まで考えて、IT人材の育成を進めてください。もし、
- 研修プラン
- 学習の流れ
- フォロー対応
こうした内容に悩んでおられるなら、ヒビノシステムまでご相談ください。